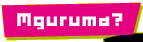「負ける気がしねぇ」
翌朝、Mぐるまが発した第一声である。
「いいちこ日田全麹をさ、売って欲しいんだよね。新規開拓で40店舗」
「営業成績で一番って面白いよ」
そう社長に告げられたのは、たった昨夜の出来事だ。
「一番」に興味がないわけではないが、何か腑に落ちないまま会社を後にした。
帰宅途中、いつものようにコンビニでメロンパンを買っている最中も、
レンタルビデオ屋で木更津キャッツアイを借りている最中も、
社長の言葉が頭の中をぐるぐる回っていた。
風呂上がりは「ビール♪ビール♪」と巨体を揺らして冷蔵庫に向かうMぐるまも、
この夜ばかりはいいちこ日田全麹をあらためて味わってみた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「いいちこ日田全麹」は原酒をはぐくむ杜
「いいちこ日田蒸留所」で醸した本格焼酎。
大麦麹だけを原酒に、永年培った麹の技の全てを傾け、
新たな味わいをつくり上げました。
全麹がひらくゆたかな旨みの世界をお楽しみください」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Mぐるまは「いいちこ日田全麹」の瓶に記されている文字を声に出して読んでみた。
「全麹がひらくゆたかな旨みの世界」
このフレーズを気に入ったらしく、何度か読み返してみたりもした。
普段の営業では口にすることのない、情緒的な表現はMぐるまの元俳優魂をくすぐった。
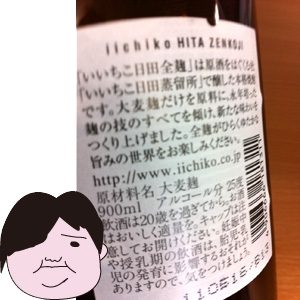
囁くように口にしてみた
「全麹がひらく…ゆたかな旨みの世界」
甘えるように口にしてみた
「全麹がひらくぅ〜 ゆたかなうまみ系のせかいぃ〜」
叫ぶように口にしてみた
「っっ全麹がひらくんだよ!超ゆたかな旨みの世界なんだよ!マジで!!」
一通り演じたところで、Mぐるまは僅かな手応えを感じていた。
「俺、日田全麹の特徴を伝えるバリエーションなら誰にも負けないかも」
約10年の俳優経験がMぐるまの背中を押した。
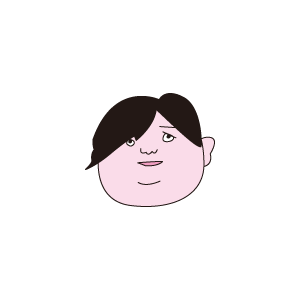
「全麹がひらくゆたかな旨みの世界」
「永年培った麹の技の全てを傾けた新たな味わい」
いいちこ日田全麹の瓶に記された印象的なフレーズを何度も繰り返した。
僅かだった手応えは、確かなものに変わろうとしていた。
「やっさい もっさい」「やっさい もっさい」
つけっぱなしのテレビから、煽るようなリズムが聞こえていた。
アルコール度数25℃のいいちこ日田全麹も、ほぼ空になっていた。
Mぐるまが「いいちこ日田全麹単独リーダー」として出社する前日の夜だった。

翌日「負ける気がしねぇ」と口にした途端に、
競う相手がいないことを思い出した。
心のどこかで拍子抜けしなかったわけではないが、
自分を納得させるのは簡単だ。
「俺は、俺に負けねぇ」
営業車のエアコンをMAXに整え、ひんやりとした車内に乗り込んだ。
Mぐるまは「暑さに負けても自分には負けまい」と
妥協とも言える小さな誓いを立てた。
昨晩練習した営業トークと演技を携えて、1件目の営業先のドアを開けた。

「どーもー!今日も暑いっすね」
10月といえども、デブネタを駆使するのがMぐるまの流儀だ。
掴みは上々。大将との会話も軽快に弾んでいる。
「大将、いいちこ日田全麹について語らせてもらえます?」
Mぐるまが切り出した。
「え?なにー?別にいいけど、なんかあったの?」
大将は、極めてライトに受け止めている様子だった。
「大将、日田全麹はいい酒なんすよ。
全麹がひらくゆたかな旨みの世界!
永年培った麹の技の全てを傾けた新たな味わいっすよ!」
昨夜の俳優魂が嘘のように、それは普段のMぐるまの言葉だった。
いつも通り無邪気で、いつも通り軽くて、いつも通りデブだった。

額に少し汗がにじんだ。
「ど、どっすか?いいちこ...日田全麹」
理想と現実。そんな言葉が頭をよぎったが、力技でねじ伏せようとした。
「なんかアツいねー。ああ、ま、考えとくわ」
Mぐるまが昨晩飲み干した日田全麹のように、さらりとシンプルな口当たりで大将は答えた。
「それよりさー、□□□□□□□□□□□□□□□」
大将の話題はメニューのデザインを変えたいんだよね。に瞬時に切り替わっていた。
どんなデザインにしたいとか、なぜ今のメニューに満足していないのだとか、
そんな比較的重要な相談すら、Mぐるまの耳には□□□としか入ってこなかった。
昨晩感じた手応えすら、大将の「さらり・するり」の口調と一緒にどこかに流された気がした。
「ここの大将には、このバリエーションがアンマッチだったのだ」
かわされた理由をこじつけて、Mぐるまは店を後にした。

次の営業先はオシャレなBARだった。
「全麹がひらくゆたかな旨みの世界かあ。永年培った麹の技ってヤツを全てを傾けたらしいっすよ」
少しだけ、すかした体(てい)を演出してみた。
俺を通じて、日田全麹を飲む客を想像してくれ!そんなメッセージが込められていた。
次の営業先はステーキハウスだった。
「全麹がひらくゆたかな旨みの世界ってヨダレ出ません?
永年培った麹の技って、まさに牛肉のために存在しますよね?」
肉押しに出てみた。
またしても、俺を通じて、日田全麹を飲む客を想像してくれ!
そんなメッセージを込めたつもりでいた。
「へーそうなんだ。考えとくわー。それよりさー....」
攻める。かわされる。ただそれだけの一日だった。

3戦3敗。
「バリエーションがアンマッチ」を裏付けるには信憑性に欠ける結果だった。
「こんなにも、日田全麹を魅力的に伝えているのに!!」
Mぐるまは納得できなかった。
「俺の演技力の問題か!?」
Mぐるまは間違った方向に進みそうだった。
「昨日はうまくいったのに!」
Mぐるまは今日が初任務だ。
「会社に戻って誰かにチェックしてもらおう」
Mぐるまは作戦自体を疑わなかった。
駐車場に車を止めて、オフィスに入ろうとした時だった。
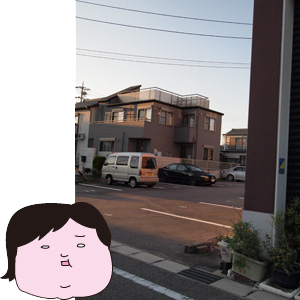
「Mぐるま、今日どうだった?」
振り向くと、社長が手招きしている。
今度はテストキッチンのドアから半分出した顔が見えた。
テストキッチンは、先輩社員や社長がよく使用する場所だ。
最近はワインに熱心なスタッフ達がメニュー開発などに取り組んでいるが、
Mぐるまはその一員ではないため、あまり馴染みがない場所でもあった。
「聞いてくださいよ!!」
Mぐるまは、テストキッチンに飛び込むや否や
昨夜から今までの出来事を勢いよく話し始めた。
はやく誰かに聞いて欲しかった。
この際、社長でもいいや。とも少し思っていた。

「….という訳で、僕の演技見てもらえます?」
興奮冷めやらぬ様子で、社長に意見を求めた時だった。
「別にいいや。知りたくないもん」
社長は、日田全麹の口当たりの如く
さらりと、するりと、きりりと、極めて冷静に断った。
Mぐるまは一瞬ハッとした。
『…あれ?…俺、もしかして図々しい?
「急に距離縮めてくるんじゃねーよ」とか、思ってるかな?
マズイ。マズイぞ!』
我に返ると、何もかも居心地が悪くなっていた。
Mぐるまの額に本日2度目の冷や汗が光り始めた頃、
社長が静かに口を開いた。

「テストキッチンをうまく使ったら?」
演技のことは完ぺきにスルーした、まさかのひと言だった。
「営業マンには提案力も欠かせないじゃない」
日田全麹の美味しい飲み方や、
日田全麹に合うメニューを提案できるようになれ。
Mぐるまは、社長が言いたいことは予想できたが
テストキッチンのテーブルに並ぶ名前も知らないイタリア食材も、
誰かの試行錯誤が伺えるイタリアンのレシピブックも、
Mぐるまの尻には小さすぎるカウンターの椅子も、
自分に似つかわしくない気がして気が引けた。

「僕ひとりじゃ無理ですよ。料理もしたことないし。」
Mぐるまはすんなりと諦めた。
実家暮らしの草食男子を気取った演技で、
「どうせ」と言わんばかりの雰囲気まで出してみた。
「Mぐるまは、ひとりじゃないよ」
社長は、まさかの甘い口調で返してきた。
「きっとすぐにわかるよ。…その時はいつでもテストキッチンにくればいい」
社長…なんか格好いいんですけど。
そんなことをぼんやり思いつつ、Mぐるまはオフィスに戻ることにした。

「きっとすぐにわかる」の意味は分からなかったが、
演技作戦が良くないんだろうとは想像できた。
「俺にしかできないやり方だと思ったのになー」
つまらなそうに席に向かうと、デスクの上に白くて大きな固まりが見えた。
誰かのイタズラかと思って手に取ると、巨大なTシャツだった。
背中には「俺の意見は通らない」の筆文字と、Mぐるまの刻印がプリントされている。
「俺の意見は通らない」とは、Mぐるまが半分冗談でよく口にするセリフだ。
Tシャツのサイズは3X。表記はアメリカサイズだが、日本サイズにすれば4L〜5L。
まさにMぐるまのサイズだった。 白い固まりを崩すとS、M、Lの3サイズも混ざっている。
その時、Mぐるまのパソコンに一通のメールが届いた。
件名は「ユニフォームです」差出人は社長だった。

Mぐるまへ
このTシャツは「日田全麹」拡販プロジェクトのユニフォームです。
リーダーはもちろん君。(実質、メンバーも君一人だが)
自分だけで考えずに、みんなの知恵を借りなさい。
テストキッチンの使い方がわからないなら、先輩に聞きなさい。
そして、もっと足を使いなさい。
ユニフォームの使い方は自由です。仲間に配ろうと(実質、メンバーは君一人だが)
お客様に差し上げようと、君が効果的と思う使い方をしなさい。
あと、今日の作戦は忘れなさい。
あれは一般ユーザーに向けたセリフです。
飲食店のオーナーが知りたがっている情報や提案について考えなさい。
PS:テストキッチンで待ってるよ
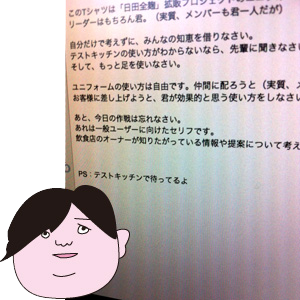
ユニフォーム。それは、Mぐるまにとって甘美な響きだった。
小学生の頃、トランペット部に入部したものの「眼科に行く」と
微妙な嘘をついて辞めて以来「ユニフォーム」に縁のない人生だった。
Mぐるまはオフィスを見渡した。
そうだ!俺には仲間がいる。力になってくれるはずだ。きっと、多分。
円陣も組んでくれるかも知れない。
なんなら「キャッツ・ニャー!」の掛け声もできるかもしれない。
Mぐるまのモチベーションは一気に昇り詰めた。
「負ける気がしねぇ」今朝と同じように力強くそう思った。
Mぐるまは斜め向かいのデスクに歩み寄って頭を下げた。
「N先輩!テストキッチンの使いかた教えてください!」
右手にはSサイズのTシャツが握られていた。
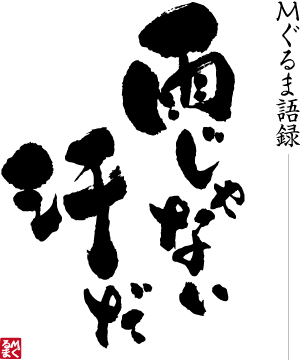
▼携帯版はこちら!
Copyright© 2011 Shibata Liquor Co., Ltd. All Rights Reserved. Produced by Powersource,Inc.